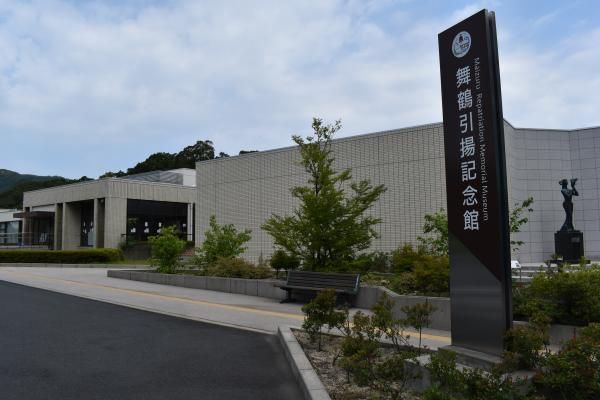岩倉具視幽棲旧宅
最終更新
王政復古はここから始まった。明治維新十傑の一人
岩倉具視は、明治維新における王政復古に力を注いだ幕末、明治期の代表的な政治家です。文政8年(1825)に参議正三位堀河康親(やすちか)の次男として生まれたのち、天保9年(1838)に公卿岩倉具慶(ともやす)の養子になります。安政元年(1854)には、孝明天皇の侍従となり、次第に朝廷内において台頭し、発言力を増してきました。そのような中で公武合体をすすめるため、孝明天皇の妹、和宮の将軍家への降嫁を推進したことにより、尊皇攘夷派から佐幕派の巨頭と見られるに至り、文久2年(1862)に攘夷運動の高まりの中で辞官落飾し、洛北の岩倉村に慶応3年(1867)までの間幽棲しました。
岩倉具視は、元治元年(1864)に大工藤吉の居宅(現在の附属屋)を購入し、主屋と繋屋を増築して住居としたのが、この旧宅です。
当史跡は周囲を塀で囲まれ、居宅は茅葺の主屋(約60㎡)と瓦葺の附属屋(約67㎡)、繋屋(約9㎡)から成ります。他に敷地の南土塀に表門を構え、門を入って主屋南庭に通じる中門、池庭、離れの便所によって構成されています。平成20年(2008)から4箇年をかけて京都市が国庫補助を得て、本格的な修理を行いました。また、敷地の東側には、展示・収蔵施設である対岳文庫(国登録文化財)と管理事務所があります。
平成25年にこの史跡を長年にわたって守り続けてこられました(財)岩倉旧蹟保存会から京都市が寄付を受け、保存していくこととなりました。
写真

岩倉具視が3年間住み、坂本龍馬ら志士たちも訪ねた、茅葺屋根の主屋。
基本情報
- 住所
- 〒606-0017 京都府京都市左京区岩倉上蔵町100
- TEL
- 075-781-7984
- FAX
- 075-781-7984
- 最寄り駅
-
京都バス 21・23系統バスで岩倉実相院下車 徒歩約2分
交通アクセス
岩倉具視幽棲旧宅には公共交通機関のご利用が便利です。
【公共交通機関ご利用の方】
地下鉄烏丸線 国際会館駅から
京都バス24系統で終点「岩倉実相院」下車南へ3分
阪急電車 河原町駅,京阪電車 三条駅 出町柳駅から
京都バス21・23系統で終点「岩倉実相院」下車南へ3分
叡山電車岩倉駅から北へ約1.4km 徒歩約20分
又は京都バス21・23・24系統「岩倉実相院」下車,南へ徒歩3分
【お車ご利用の方】
専用駐車場がございます。詳細は管理事務所へお電話ください。 - URL
- URL
- iwakura-tomomi@ueyakato.co.jp
- 開館時間
- 09:00 ~ 17:00 (最終入館時間 16:30)
- 夜間開館
- 無
- 入場料
-
通常時: 有料
特別展示料: 有料
入場料
一般 300円
中学・高校生及び高等専門学校生 200円
小学生 100円
※特別なイベントなどの際に、入場料と別途特別料金が必要になる時があります。
入場料の免除の方
・京都市内在住の70歳以上の方:ご本人無料
※敬老乗車証,運転免許証等住所と年齢を証明できるものをご提示ください。
・京都市内在住の70歳以上の介護保険被保険者証をお持ちの方:ご本人及び介護者1名無料
※要介護または要支援の認定を受けた方に限ります。被保険者証をご提示ください。
・身体障がい者手帳,療育手帳,戦傷病者手帳,被爆者健康手帳,精神障がい者保健福祉手帳等をお持ちの方:ご本人及び介護者1名無料 手帳等をご提示ください。
・京都市内の小・中学生:ご本人無料 市内在住の児童・生徒及び市内の学校に在校する児童・生徒が対象です。生徒手帳等を提示するか,申告してください。 - 休館日
- 水曜休館(ただし、水曜が祝日の場合は翌平日が休館)、12/29~1/3休館
- ユニバーサル設備
- 申し出による授乳室
- 施設からのバリアフリーについてのコメント
- 施設内に段差があるため、足元の不自由なお客様は事前のご連絡をお願いいたします。
こちらの基本情報は掲載時点のものであり、変更される可能性がございます。
最新の情報は公式サイトにてご確認ください。